アライドファン.comは、佐々木ネットワークテクノロジーズが運営する、ネットワーク技術情報サイトです。
佐々木ネットワークテクノロジーズ
〒761-8073 香川県高松市太田下町2456
NAT(Network Address Translation)とは、パケットヘッダに含まれるIPアドレスを、別のIPアドレスに変換する技術である。
グローバルIPアドレスが枯渇しているため、LAN側のアドレスには通常プライベートIPアドレスが使用される。
このプライベートIPアドレスのままでは、インターネットに接続することができない。
そのため、ルータに1つのグローバルIPアドレスを割り当て、LAN側の複数のホストでそのグローバルIPアドレスを共有することにより、プライベートIPアドレスのネットワークからインターネットに接続する。ここで必要となるのがNATである。
なお、静的NATはスタティックNATと、動的NATはダイナミックNATと呼ばれることがある。
また、静的NATは、1対1NATと呼ばれることもある。
静的NATでは、LAN内部の1つのIPアドレスが、常に1つのグローバルIPアドレスに変換されるため、端末の数だけグローバルIPアドレスが必要となってしまう。そのため、複数の端末で1つのグローバルIPを共有するには、動的NATを使用する必要がある。
LAN側の特定のサーバをインターネット側に公開する場合は、動的NATと静的NATを併用する。すなわち、一般の端末に対しては動的NATを、公開するサーバに対しては静的NATを設定すればよい。
,
ENATは、NAPT(Network Address Port Translation)、NATオーバーロードといった別の名前で呼ばれることもある。
さらに、CiscoはPAT(Port Address Translation)、LinuxではIPマスカレードと呼んでいる。
このように、1つの技術に対して複数の名前が存在するので、注意が必要である。
通常の動的NATでは、LAN側の複数台の端末が同時にインターネットアクセスしようとしても、ルータにはインターネットからの戻りパケットを届ける端末がわからないため、インターネットにアクセスすることができない。
ENATを使用すると、1つのグローバルIPアドレスの中のポート番号によって、LAN側の端末が区別できるようになるため、複数台の端末が同時にインターネットにアクセスできるようになる。
そのため、インターネットアクセスルータでは通常「動的ENAT」が使用される。
参考ページ : 機器設定方法−ARシリーズルータ NAT設定方法(1)
(この下は自動配信されるネット広告スペースです)
グローバルIPアドレスが枯渇しているため、LAN側のアドレスには通常プライベートIPアドレスが使用される。
このプライベートIPアドレスのままでは、インターネットに接続することができない。
そのため、ルータに1つのグローバルIPアドレスを割り当て、LAN側の複数のホストでそのグローバルIPアドレスを共有することにより、プライベートIPアドレスのネットワークからインターネットに接続する。ここで必要となるのがNATである。
動的NATと静的NAT
NATには、IPアドレスを1対1で固定的に変換する静的NATと、多対多で動的に変換する動的NATがある。なお、静的NATはスタティックNATと、動的NATはダイナミックNATと呼ばれることがある。
また、静的NATは、1対1NATと呼ばれることもある。
静的NATでは、LAN内部の1つのIPアドレスが、常に1つのグローバルIPアドレスに変換されるため、端末の数だけグローバルIPアドレスが必要となってしまう。そのため、複数の端末で1つのグローバルIPを共有するには、動的NATを使用する必要がある。
LAN側の特定のサーバをインターネット側に公開する場合は、動的NATと静的NATを併用する。すなわち、一般の端末に対しては動的NATを、公開するサーバに対しては静的NATを設定すればよい。
,
NATとENAT
ENATとは、IPアドレスの他にプロトコルやポート番号も同時に変換する動作のことをいう。ENATは、NAPT(Network Address Port Translation)、NATオーバーロードといった別の名前で呼ばれることもある。
さらに、CiscoはPAT(Port Address Translation)、LinuxではIPマスカレードと呼んでいる。
このように、1つの技術に対して複数の名前が存在するので、注意が必要である。
通常の動的NATでは、LAN側の複数台の端末が同時にインターネットアクセスしようとしても、ルータにはインターネットからの戻りパケットを届ける端末がわからないため、インターネットにアクセスすることができない。
ENATを使用すると、1つのグローバルIPアドレスの中のポート番号によって、LAN側の端末が区別できるようになるため、複数台の端末が同時にインターネットにアクセスできるようになる。
そのため、インターネットアクセスルータでは通常「動的ENAT」が使用される。
参考ページ : 機器設定方法−ARシリーズルータ NAT設定方法(1)
バナースペース
佐々木ネットワークテクノロジーズ
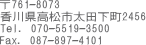
Mail. inq09@allied-fan.com